藍染とは
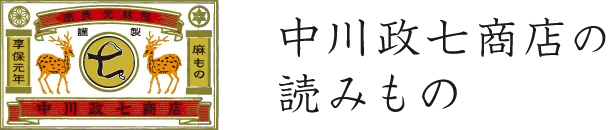
江戸っ子に親しまれたジャパン・ブルーの歴史と現在
日本人の生活に深く根付いてきた「藍染(あいぞめ)」。
武士の時代には「縁起の良い色」として好まれ、明治には海外から「ジャパン・ブルー」と称えられた、日本を象徴する色でした。
今日は、そんな藍染の歴史と魅力を追ってみます。
藍染とは。「ジャパン・ブルー」は日本の染色文化の象徴であった
藍染とは植物染料「藍」を用いた染色技法。また、染められた布地そのものを藍染と呼ぶこともある。用いる植物は日本で主流のタデアイのほか、沖縄の琉球藍、インドではマメ科の木藍など、地域によっても異なる。これらから抽出される「インジゴチン」という色素を持つ染料を総称して「藍」と呼ぶ。

藍の色素は不溶性(液体に溶けない、または溶けずらい)のため、他の染料植物と同じように煮ても色素は取り出せない。そこで、藍を甕(かめ)に入れて発酵させたり、還元剤(酸化物から酸素を取りだす薬剤)を用いたりして藍液をつくる。この作業を「建てる」という。こうしてできた藍液に糸や生地を浸し、その後、空気にさらすと直後は黄土色となり、徐々に酸化して青に発色していく。

この作業を繰り返すと青に濃淡が生まれる。
藍染といえばこの人。独自の絞り染を確立した片野元彦さん

合成染料や海外産の安価な藍の台頭により、国産の藍は激減してきた。そのため、伝統的な藍染は「本藍染」や「正藍染」、「天然藍」などと区別して呼ばれるが、中でも天然藍を生かして独自の絞り染を確立したのが、染色家の片野元彦だ。
もとは洋画家を目指していた片野氏であったが、師事していた画家の岸田劉生が30歳の頃に急死すると、染物に専念しだす。その後、57歳から藍染を始めると、染色家の芹沢銈介のもとで技術を学び、亡くなる76歳まで染色家として活動した。

そんな片野氏が生み出したのが「片野絞」。

